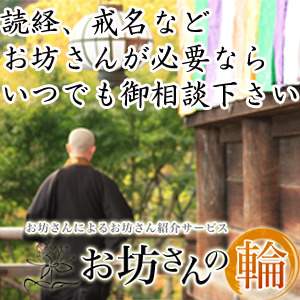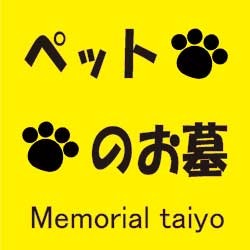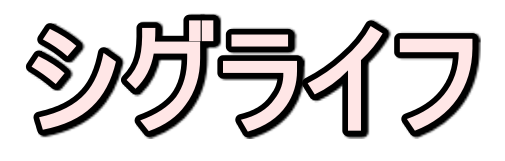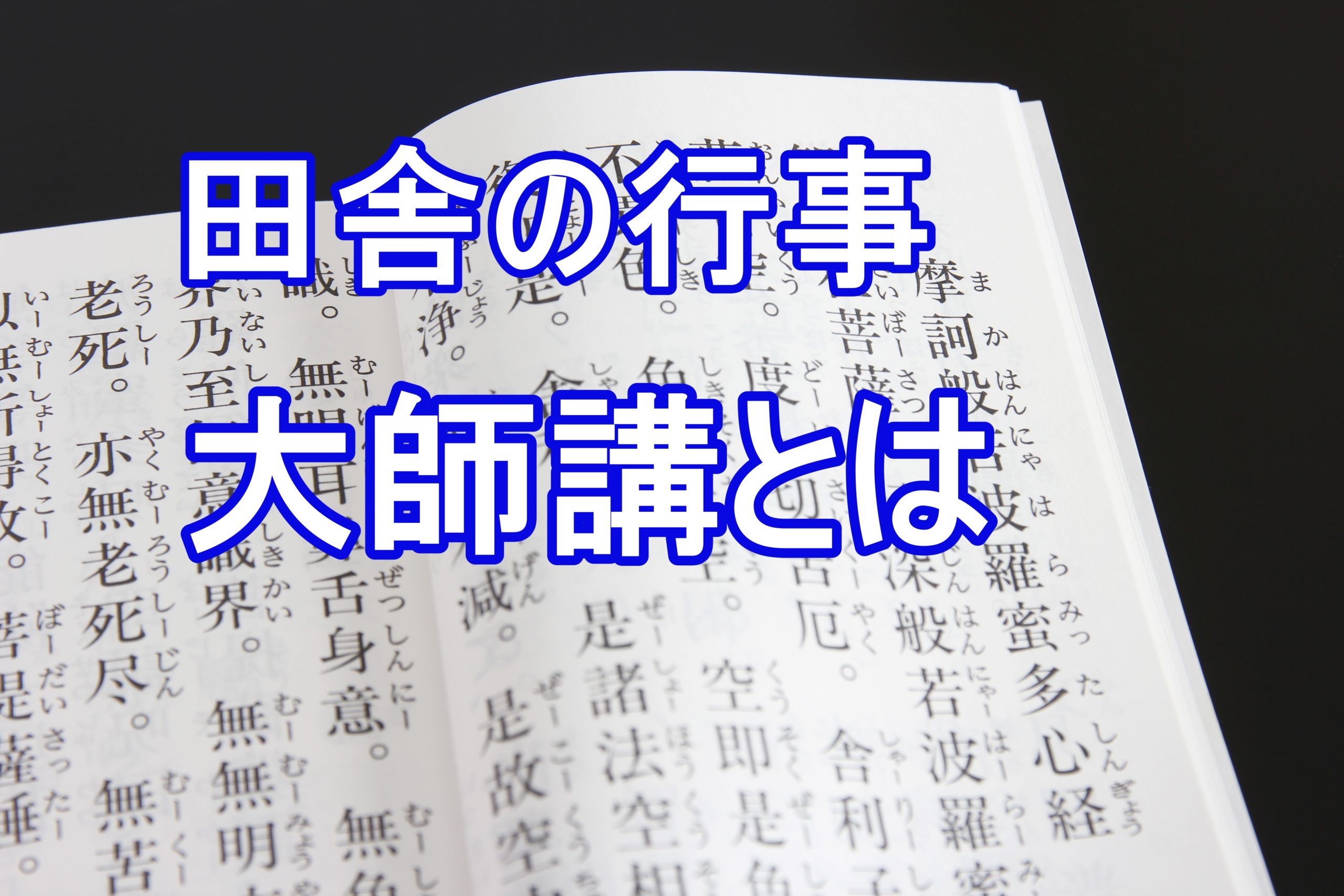田舎オヤジの暮らす地域では、毎月21日は『大師講の日』となっている。
大師講とは、11月23日の夕方から24日にかけて行わる民間行事なのだが、
真言宗が多いこの地域では毎月21日に
弘法大師である空海の命日に近所で集まりお経を唱えて
報恩のために行う講のことを大師講と言っている。
しかし、所変わればで隣の班(地区班)では20日に大師講を行っている。
要するに大師講をすることに意味があり、日にち(命日)など
あまり気にしないあたりさすが田舎というところだ。
大師講とはお大師さんを拝むだけじゃない!
田舎オヤジの所でする大師講には、
お経を拝む以外にも大事なことがある。
それは、大師講で近所が集まるのを利用して
町行政の広報や町内会の連絡事項、協議事項をする場になっている。
これのおかげで町内会長さんや班長さんなど急ぎでない場合は、
この月一に集まる大師講のおかげで
各軒へ一軒一軒出向かなくて済むのだ。
田舎はとにかく何でも自分たちで解決しなければならない事が多いので
この大師講が重要な役割を果たしている。
同じ地域でもほかの町内会では、
大師講をしていない、していたが諸事情で止めたところも多い。
田舎オヤジの住む地域で大師講をしているのは、二つの町内会だけだ。
なのでかどうかは分からないが、
田舎オヤジの町内会は、まとまりがあるように思える。
人の集まりの悪い町内会は、
みんなで物事を相談して決めずに独自で動くからまとまりにくいのだ。
みんなのスマホに通知ができる田舎オヤジの大師講
前置きが長くなったが、今回は田舎オヤジの自宅が
大師講の当番家に当たっている。
以前は軒数も多かったので年に一回周ってくればいいほうだったのが
最近では7軒にまで減ったので年に2回周ることもある。
朝から、家中の大掃除である。

我が家は家族が多いのでいくら掃除して
片付けてもすぐに物が散乱する。
(特に一番下の息子が原因)

今日も片付けてる後から子供のおもちゃが散らばっている。
それでは田舎オヤジのところの大師講のやり方を紹介する。

準備は、弘法大師の掛け軸に不動明王の掛け軸を床の間に掛け
高野まきにお酒とお供え物、仏具を並べるだけのシンプルなものだ。
ここで皆で仏前勤行次第を拝む。

みんなが揃うまでの間、ここで雑談が始まる。
雑談が長引いて肝心の般若心経を拝むのが遅くなることはよくある。
いつも誰かが口火をきり、お経を拝むことになる。

仏前勤行次第を拝む直前にお酒のフタを開け、ろうそくに火をつけ
線香を三本立て火をつける。
次の当番家に当たってる人が頭(とう)になって拝む。

般若心経が始まった頃くらいに当家はお茶を配る。
まず最初は、主役である弘法大師にお茶を出す。
(最初は知らなくて手前の人からお茶を出して怒られた苦笑)
次に先頭の頭(とう)をとっている人に出し
後は、上座に座ってる順にお茶を出していく。
拝み終わったらまた雑談が再開される(笑)
この時に、連絡や決め事などがあれば
話題に出してみんなで相談するのだが、
多くの時間は雑談に費やされる。
時に雑談の中に有益な情報が混ざっていたり、
誰かがケガした入院しているなどの時事ネタなどがあったりと話が弾む。
※今回は感染防止のために雑談は止めてすぐに大師講が終わった。
お経だけ読んでほしい。そんな時はお坊さんの輪でお坊さんを呼んで下さい。まとめ
以前は、お供えした一升瓶の酒を皆で飲み干すまで帰らなかったりと
派手なこともしていたが、時代の流れと共に
お茶を飲むだけに規模を縮小した。
よく田舎の行事は面倒くさいというが、
簡単に出来るように改善すれば良いのである。
とかく田舎の行事をなくそうという動きがあるが
今まで述べたように何かしらの意味が
その行事にはあるということだ。
昔からその地域で暮らす上で必要だから出来た行事なのである。
だからといって昔ながらのやり方をするから
時代に合わないのである。
今の時代に合ったように改善すれば良いのである。
そのうえで、必要のないものは削って
未来にも続けていけるようにすれば田舎の良さも保たれるはず。
(悩みの無料相談の申込み)